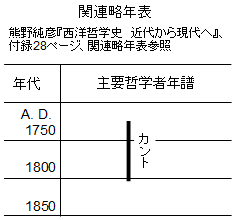人間理性の限界
デカルトからヒュームまでの近代哲学をまとめて、ひとまずその終着点を与えたのがカントです。デカルトからイギリス経験論までの流れを、カントがどのように引き受けたかを見てみるのが、彼の思想を知るための足掛かりになってくれるでしょう。ただしここでは、広大なカント哲学のごく一部、世界の認識に関わる議論だけを取り上げさせてもらいます。
1.理性の哲学の変遷
デカルトを代表とする十七世紀の理性の哲学者においては、神的理性を後ろ盾にすることで、世界に対する確実な認識を手に入れることができると考えられていました。十八世紀になると次第に、人間理性は神的理性の後見を脱した「啓蒙的・批判的理性」と捉えられるようになります。しかし元々は、神的理性を後ろ盾にすることで世界に対する確実な認識を手に入れることができると考えられていたので、神的理性の媒介がなくなったときには、世界の認識における調和が保証されなくなってしまいます。結果として、いわゆる理性主義的な形而上学は、その末期になると次第に独断論の色を濃くしていきました(ここに包含しきれない、ライプニッツのような人たちもいます)。
このような流れに対する反省として、ロック、バークリ、ヒュームらイギリスの哲学者たちは、われわれに確実な認識を与えてくれるものと考えられてきた「生得観念」や、それにもとづく理性的認識の存在を否定し(あくまで否定したのは形而上学的概念としての理性)、われわれのもつ観念はすべて感覚的経験を通じて手に入れられるのであり、すべての認識は蓋然的なものとみなす経験主義の方向をとりました。その立場をとるとやはり、それまで成立していた数学や数学的自然科学の確実性を主張することはできなくなります。
2.イギリス経験論からカントへ
理性主義的形而上学では、感覚的経験では得られない理性的観念として、数学的観念の他に「神」とか世界とか実体(さまざまな感覚的諸性質の背後にあって、それらをまとめ、支えている基体)とかの観念もそこに数え上げていました。こういった観念にも数学的観念と同様に客観性を認めて、認識の体系を作り上げてきました。
それに対しイギリスの「経験主義」は、そのような「生得観念」や「理性的観念」を認めることから生じる弊害に気づいて、われわれのもつ観念はすべて「経験的観念」だと考えるようにしました。そうするとやはり2+3=5のような数学的観念も蓋然的真理でしかないことになり、カントはここに疑問をもちました。こうして、神的理性の媒介を拒否しながらもなお、数学や数学的自然科学の確実性、つまりは我々の理性的認識と世界の数学的合理性の調和を保証しようとして、理性の自己批判を行ったのが、カントの『純粋理性批判』です。
3.カントによる認識論
3.1 カントの生涯
カントは生まれ故郷のケーニヒスベルク(現ロシア領カーニングラード)を一度も出ることはありませんでした。ここの大学で哲学を学び、家庭教師や私講師をしたあと、四十六歳になってやっと教授になります。主著『純粋理性批判』を刊行したのは五十七歳で、続いて『実践理性批判』と『判断力批判』を書いています。非常に静かな人生を送ったカントですが、彼の思想により「カントは神様の首を切り落とした」と言われることもありました。それは彼の認識論におけるある特徴によります。
3.2 物自体と現象界
カントもデカルトと同じように、人間理性の限界を見て取っています。カントは物それ自体の姿を「物自体」とよび、けっして人間が見ることはできないと考えています。我々は確かに物の姿をその対象に見ているのですが、それは我々の認識の形式により制限される「現象」としての現れにすぎません。物自体である対象から、我々の理性の形式によって切り取られて現れる世界を、彼は「現象界」と呼んでいます。
3.3 直観の形式と純粋悟性概念
カントは、我々の理性が発動する形式を二種類に分けて考えています。物自体によって与えられる材料を受け容れる形式と、そうやって受け容れた材料を整理する形式です。前者が「直観の形式」で、空間と時間がそうだと彼は考えています。我々は目の前の対象に空間的な拡がりと場所の占有を読み取っていますし、経験可能な事態は時間の流れの中で刻一刻と変化していきます。彼の考えでは、空間や時間といった主観の側の形式があって、その形式に当てはめられることで初めて現象として現れてきます。
後者は直観の形式により受容された材料を整理するための形式であり、われわれの論理的思考形式です。カントは十二の基本的な思考形式を導出し、「純粋悟性概念」、「思考のカテゴリー」と呼んでいます(表1)。
表1 幾分簡略化したカテゴリー表(木田元『反哲学史』164ページの表参照)
| 量 |
単一性 |
数他姓 |
全体性 |
| 質 |
事象内容性 |
否定性 |
制限性 |
| 関係 |
実体と属性 |
原因と結果 |
相互作用 |
| 様相 |
可能性 |
現実性 |
必然性 |
例えば原因と結果の関係もわれわれが受容した材料を整理するための形式の一つです。空間的な拡がりを持って捉えられる対象が、時間の経過に伴い変化していくその姿に、変化の前にあってその変化をもたらす原因と、変化の後に残る結果という因果関係を見ています。
3.4 それがそれとして現れること
上で見たようにカントの考えでは我々は、空間・時間という直観形式を通して受け容れる感覚与件に、思考のための網の目(カテゴリー)を通して現象を認識しています。確かに我々は空間・時間という抽象的な形式で対象を捉えているのですが、1歳や2歳の赤ちゃんがそんなふうにして物事を捉えているとはとても思えません。対象が対象として主観に現れるということに、必ずしも空間や時間といった抽象的形式が必要というわけではないでしょう。魚や鳥、ネコとイヌなど、少なくとも脊椎動物においては、これらの抽象的形式など介さずに、そして彼らは「反射共和国」などではなく、それをそれとして認識していると確信をもって言うことができます。
それがそれとして現れるということに「認識」の言葉をあててよいと思われますが、カントの悟性概念による認識論は、そのような原初的な認識とは異なる、知性による現実認識であると考えられます。動物においても起こっているはずの、対象の現れとしての認識を議論するには、20世紀に花開いたゲシュタルト心理学や動物行動学を待たないといけないでしょう。
3.5 超越論的主観
我々に現れてくるのは物自体としての世界そのものではなく、我々の知覚・認識装置によって大きく制限された、直観と認識(悟性)の形式を通しての現象です。一方でこれらの形式を通して現象が現れるということは、物自体の世界は別にして現象界だけであれば、その形式的構造に関して人間が作り出していると言えなくもありません。ということは人間理性自ら作り出す形式的構造に関してなら、先験的(アプリオリ)に、したがって確実に、認識しうるということになります。我々の理性が現象界の在り方を決定している、と言い換えることもできるでしょう。こうして現象界に限定されてはいるのですが、神的理性の後見なしに、人間理性は世界に合理的構造を与える「超越論的」主観であることになります。
4.カントの神学的思考
4.1 神の存在証明
カントにおいては、経験そのものを可能にする先験的な形式が存在するのでした。先験的な形式が及ばない、つまり経験を超えている対象については、一般にどのような認識も成立しない、とカントは考えたようです。そこから四つのアンチノミーが出てくることになります。ここではそのうちの一つだけ引用しておきます。
「世界は、有限であるとも無限であるとも語ることができない(第一アンチノミー)。」
「神の存在を理論的に証明することは、どのようにしても不可能である(純粋理性の理想)。」(熊野純彦『西洋哲学史 下巻』第八章)
単純化して言うと、世界には始まりがあるともないとも言えないので、世界のはじまりである神が実在するとは言えない、ということです。デカルトが神の本質には実在性が含まれているから神は実在すると言っており、カントはこういった議論を批判しています。デカルトの神の存在証明において言われていることは、もっとも実在的なものという主語概念が、「存在する」という術語概念をふくむ、ということだけです。これは神という言葉が定義されるときに、存在するという性質が含められて成立した、ということにすぎません。本質として存在する(と考えられている)ことと、事実、存在することは別のことです。事実存在の本質存在への回収という、古代から続いて近代哲学をも規定している事態を、カントは批判していることになります。
4.2 さらなる理性の確定へ
カントが否定したのは神の実在証明であって、彼自身が神が実在しないと言ったわけではありません。カントはある種否定神学的(不在であることをもとにして)に神について考えていて、彼が神の実在を信じていなかったとはとても思えません。カントの神学的思考は、その後の倫理的規定を強く含む、『実践理性批判』、『判断力批判』、『恒久的世界平和のために』などの著書においても基付けになっているのではないでしょうか。
カントの表現はなかなかに情熱的であったりします。『実践理性批判』のむすびの一句を引用して、長くなったこのページを終えたいと思います。
「ふたつのものが、それを考えることが多く、かつ長ければ長いほどますます新たに、また増大する賛嘆と畏敬をもってこころを満たす。それはすなわち私の頭上にある、星が鏤められた天空であり、私のうちにある道徳法則である。」(熊野純彦『西洋哲学史 下巻』第八章)
- 参照文献1:熊野純彦『西洋哲学史 近代から現代へ』(岩波書店)
- 参照文献2:木田元『反哲学史』(講談社学術文庫)
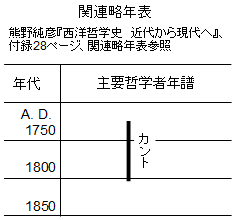
<< モナド論 自己を認識する自己 >>