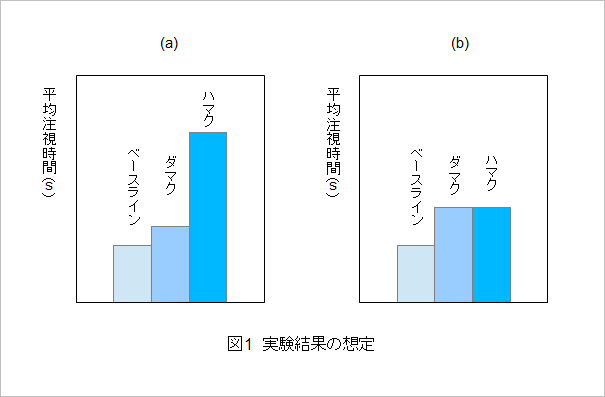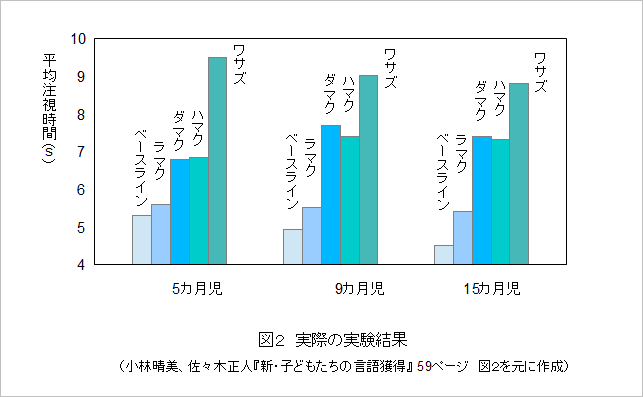サイト全体を見たいときはサイトマップをご覧ください。
目次
1.評価
評価:
中沢新一による文化人類学の人気シリーズ、「カイエ・ソバージュ」シリーズの第一冊目です。文化人類学の「入門書」というわけではないですが、おそらくもっとも読みやすく、かつ文化人類学がどういう学問か垣間見せてくれる良書です。自分も文化人類学はこの本から入りました。
一冊目である『人類最古の哲学』では、現代に伝わる民話やおとぎ話から、神話の思考の特徴を取り出してみよう、という感じの内容になっています。神話にはその社会の構造が反映されているみたいで、社会内の不均衡を媒介物により解消しようとする、そういった特徴があると述べられています。こういった解釈には、現代社会の非対称性を解決する糸口を見つけたい、そんな思惑がもとになっている気がします。
カイエ・ソバージュシリーズは全5巻で、読み返したのはまだこの一冊なので、シリーズ全体がどんな感じだったかは忘れてしまいました。いったんこの本だけで、章ごとの要約をしながら内容を整理してみようと思います。
2.章ごとの要約
序章 はじまりの哲学
神話は人間が最初に考え出した最古の哲学だと言えます。現生人類における異なる認識領域の間の流動性という特性が、神話のもとづけとなっていると考えられます。新石器時代に新石器革命と呼ばれる農業や動物の家畜化が行われ、そしてこの時代に思考の組織化もおこり、神話のベースがつくられたのではないかと推測できます。また、この人類最大の革命は、旧石器時代の狩猟民たちの知識と体験の集積がベースになっていると考えられます。
神話の論理は通常の論理とは違って「感覚の論理」をもちいており、「具体的な感覚素材を象徴的な「項」にして、それらを論理的に組み合わせることで、世界の意味や人間の実存について考え抜こうとしています。」(p.15)。一方で、神話では動物や植物の生態や分類の膨大な知識がもとになっていて、科学との類似性を見せます。しかし神話ではそれぞれの領域に流動的な通路を開くものとして人間に生まれてきたものなので、現代の考え方では全く理解できない筋立てなどが登場します。
第一章 人類的分布をする神話の謎
よく似た内容の神話が世界中で見つかっていて、それはよく似た思考が保存されながら、人類の移動に伴って少しずつ変化していったためではないかと考えられます。南方熊楠は「燕石」の研究を行っていて、「燕石」の物語は「結婚しない娘」または「結婚したがらない娘」の話です。美しい深窓の令嬢が求婚者を袖にしながら、結局は他の動物と結婚したり、はるか異界の地に旅立っていくというのが大まかな話で、この枠組みを共有する物語が世界中にあります。日本では「竹取物語」がこれにあたります。
燕石の要素を持つ物語は、南方熊楠によるとだいたい七つの要素から成っています(ここでは省略)。そこでは燕という動物の性質、特殊な鉱物と植物の間に関係性を見出し、一貫した野生の思考の論理によって、たがいに関連づけられているのがわかります。
第二章 神話論理の好物
人間の文化でいつもとても大きな働きをしているものに豆があります。日本では節分において豆が使われます。豆は「生者と死者のそれぞれの世界の境目にたって、ふたつの世界のコミュニケーション回路を開いたり閉じたりする役をする」(p.67)とても複雑な性格をもつ両義的なものです。また「広い地域で共有されていた神話的思考において、「豆」は男性性の中の女性的なものをあらわすと同時に、女性性の中の男性的なものをあらわします。つまり対立しているもの同士を仲介する働きを「豆」は持っていたことになります。」(p.71)。
ピタゴラスは自身の教団において、豆を食べることと燕を家の中に入れることを禁止していました。豆は生と死を仲介する両義的な存在でしたし、燕は水界に馴染む死の領域に近い恐るべき動物だと考えられていたからです。ピタゴラスは神話的思考と多くの共通点をもつ考え方を持っていましたが、神話的思考を否定しようとした最初の西欧哲学者だとも言えます。
第三章 神話としてのシンデレラ
神話的思考の「残骸」とでも言えるものに「シンデレラ」があります。残骸と言っても、とても美しいみごとな形を持っています。シンデレラ・ストーリーには社会的に高い人と低い人に分離された状態から、仲介によってこれらを結びつけるという、目的があります。シンデレラの仕事場である「カマド」は生者と死者の世界を仲介する場所であり、仲介機能によって、現実世界の不均衡に調停をもたらす役目を持ちます。このようにかつては民話が、現実では決して解決できない矛盾を幻想的に解決する役目を担っていました。
第四章 原シンデレラのほうへ
ほとんどの民話はたくさんのバージョンを持ち、神話も同じでお互いに変形しあって新しく作り変えられていきます。グリム兄弟の「灰かぶり少女」もシンデレラの一つのバージョンで、一般的なシャルル・ペロー版よりも原形をとどめた古いものとなっています。こちらの版では、媒介として灰だけでなく小鳥、豆、鳩、ヘーゼルの木、母親の霊が次々と登場してきます。神話はその論理にしたがって、仲介者を連続して関わらせることで、仲介機能を実現しています。
第五章 中国のシンデレラ
ポルトガルの民話に「カマド猫」というシンデレラの物語があります。この民話では、少女自身が水の中に入って魚との結婚を行うことで、転換が起こります。水界の異性との結婚は神話ではたびたび登場しており、折口信夫によると、これは「族外婚」の問題を反映していたと考えられています。「このポルトガル版シンデレラでは、死者や異界のものたちとのコミュニケーションの回路を開くことの重要性が語られていることがわかります。」(p.131)。
九世紀の中国でもシンデレラの物語が記述されています。この物語では魚の骨が重要な役割を果たし、シャルル・ペロー版と同じく、宴からあわてて戻った娘が残した片方の靴によって、娘は国王の妻となります。捨てられてしまった魚の骨のところは、経済よりも贈与に関わっているといえますが、この中国版のシンデレラには、あからさまな経済的欲望が入り込んできています。
第六章 シンデレラに抗するシンデレラ
北米インディアンのミクマク族は、フランス系カナディアンから教わったシンデレラ物語を、鋭い批評精神をもって作り直しました。ミクマク版シンデレラでは「ボロボロの肌」の少女が、父親からもらったブカブカの靴をはいて、狩りの名手である「見えない人」のもとに、自らおもむいていきます。そして美しい心を持った「ボロボロの肌」は「見えない人」の姿を見ることができ、彼の妻となります。この物語ではヨーロッパ版における女性の受動性や外見への偏執が批判されています。
第七章 片方の靴の謎
シンデレラは片方の靴を残して王宮を去ります。レヴィ=ストロースはオイディプス神話群と関係があると推測しているようです。オイディプス神話では、跛行、なぞなぞ、近親相姦、盲目といった重要な要素が含まれています。イタリアの歴史学者ギンズブルグによると、片足が不自由なことは人間が大地から生まれ、そこにしばられた存在であることと関係しています。オイディプスが片足を引きずっているのは、彼がそこから生まれそこへと還っていく、死者の領域に片足をつっこんでいるためです。そしてシンデレラも生と死の領域を仲介する存在でした。ギンズブルグによると、シンデレラの片方の靴は死者の国(王子の王宮)にいったものの印なのです。
ロシアからトルコ・ギリシャにかけて広く伝承される「毛皮むすめ」の物語では、父親からの近親相姦を嫌った娘が、動物の毛皮をかぶって王宮に身をかくしています。このようにシンデレラ物語とオイディプスの神話には明確な関連性が認められます。一方で、神話的思考と資本主義との結びつきをシンデレラの物語に見出すことも可能です。
終章 神話と現実
神話の思考方法は、具体的に世界と深く結びついた素材が用いられています。神話のもととなった具体性の世界は、現代の視覚と聴覚にかたよったものではなく、五感にもとづいた複雑な世界でした。人間は合理化により、現実世界のあまりの豊饒さを取り除いて、人間の思考と行動で制御できる領域を囲い込んできました。
インドの古代宗教の「ソーマ」は幻覚作用を持つ「ベニテングダケ」を「三つのフィルター」を通して利用可能としたものと考えられています。三つ目のフィルターはバラモン自身の身体で、彼らの身体を通してろ過された尿をミルクに混ぜて飲んでいたようです。実は2000年前からソーマの代用品がソーマとして使われていて、代用品で儀式が可能なのは、現実から乖離した幻想や想像力を利用する宗教だからであり、神話ではそうはいきません。イテリメン族の「ベニテングダケ娘」の神話は、現実と幻想の間のバランスの重要さを、我々に警告してくれています。
3.追記
ずいぶん長くなりましたが、章ごとに要約してみると、民話に残された神話的思考を紡いで、神話の思考方式を取り出してみよう、そして現代の問題の根源にある思考方式の変遷をそこに見出そう、という流れが見えてきます。燕、媒介、豆、死者、カマド、水界、その他あらゆる項が螺旋を巻いて、順次連接していっています。この本の構成自体が神話的思考をなぞるように成されています。
文化人類学の本なので、いくつかモデル図(p.68、p.118、p.127)が載せられてましたが省略してます。
文化人類学は構造主義の名で呼ばれることも多くて、この構造は抽象化された概念を用いたモデルのことです。モデル化は文化人類学の魅力の一つで、でも今回の本ではモデル図は特に必要ないとも感じました。図式化が上手くいかなかったのが、レヴィ・ストロースの後継が続かなかった理由なのかな、と勝手に思ってたりします。
それからたくさんの物語が記述されているんですが、ほぼ全部その内容は飛ばしてます。民話や神話の具体的な記述は、ぜひ著書の方で確かめてみてください。
4.広告
新装版が出てるみたいなんですが、新装版と自分の読んだ版の違いがあるかもしれないので、電子書籍の旧版の方を貼っておきます。自分は圧倒的に紙媒体派なんですけどね。

<< 竹田青磁『現象学入門』書評と要約 大澤真幸『我々の死者と未来の他者』書評と要約 >>
<< 書評トップページ
ホーム