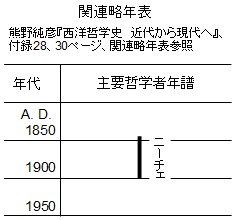力への意志
形而上学的思考様式を克服しようとした試みを、もっとも壮大なスケールで展開したのはニーチェだと言われています。木田元によると、ドイツ哲学にはつねに認識よりは意志を、表象よりは意欲を重視する伝統があるそうで、ニーチェもこの伝統を踏まえた上で、それを乗り越えるかたちで、自分の「哲学」を形成していきます。
1.ニーチェの生涯
まず彼の生涯を簡単に見ておきましょう。ニーチェは1844年にライプチヒ近郊に生まれます。彼は早熟の才能の片鱗を示しており、ボン大学の神学部に入り青春を謳歌するのですが、この時期に梅毒に感染してしまいます。一年後、心を入れかえてライプチヒ大学に移り、古典文献学に専念します。
ニーチェはライプチヒ時代にショーペンハウアーとリヒアルト・ワーグナーの呪縛と言っていいほどの多大な影響を受けます。当時、古典文献学徒としてすぐれた才能を発揮したニーチェは二十五歳になる直前という若さでバーゼル大学に助教授として招かれます。古典文献学者としてのニーチェの専攻領域は、通常「ギリシア悲劇」と呼ばれている芸術様式が成立してくる時代です。これは「フォアゾクラティカー」たちの活躍した時代と重なります。
ニーチェの処女作『音楽の精神からの悲劇の誕生』は、精緻な実証を売り物にしていた当時の古典文献学の論文のスタイルを大きく逸脱していました。当時のヨーロッパでは、古代のギリシア芸術の特徴から、古代ギリシア人は晴朗で楽天的な民族だと思われていました。しかしニーチェは、古代ギリシア民族の奥底には激情的で暗い厭世主義が横たわっていて、それを克服するために華々しい造形芸術を創造したのであり、それら二つの相反する原理が調和を実現したときに、「悲劇」という様式が成立したと主張しました。
この著書に対しては痛烈な批判がくわえられ、古典文献学界からいわば葬り去られることになりました。健康状態の悪化もあって、1879年にはバーゼル大学を辞め、年金をたよりに在野の思想家として生きてゆくことになります。このころからワーグナーやショーペンハウアーの呪縛から解き放たれ、独自の思想を模索し始めます。
1880年代に入ってまず、『ツァラトゥストラはこう語った』を完成し、今度は本格的に「哲学的主著」の執筆にとりかかるのですが、89年に精神的危機によりその活動は停止されてしまいます。彼は1900年まで生きるのですが、彼の思想的営みは、ほぼ1888年いっぱいで終わったとみれます。
2.生成する自然
2.1 力への意志
ニーチェはヨーロッパの哲学を本質的にはプラトン主義だとみなしていて、ヨーロッパの形而上学の歴史をニヒリズムとしてとらえようとしていたようです。彼によると、これらの哲学は肉体から分離された精神にのみ近づきうる超自然的原理を設定し、それとの関連において自然界のもろもろの存在者の存在を理解していました。ヨーロッパ文化はこうした形而上学にもとづき、自然から離脱する方向で形成されてきたのですが、形而上学的原理が本当に存在するわけではないので、いくら追い求めてもそこに行きつくことはありません。その徒労に疲れて、ヨーロッパ文化が全体として指導原理を失ったところに、19世紀中葉のニヒリズムが生まれてきた、彼はそのように考えました。このニヒリズムの克服が彼の哲学的主著の主題となります。
ヨーロッパのニヒリズムは西洋形而上学によって「自然」が単なる素材に貶められてしまったことに起因しているので、生成原理をそれ自身に内包する生きた自然を回復することで成し遂げられるはずです。「力への意志」とは、そのような生きた自然の「生」を言い表すために使用された言葉です。ところでショーペンハウアーの「生(レーベン)」、「意志」の概念も類似の意味を持ちます。しかし彼が「意志」と呼んでいるのは人間の意志のようなものではなく、すべての生命が持つ生への衝動のようなものです。彼にとっては、生命の世界は方向性を持たない衝動の世界であり、それに対してニーチェが「力への意志」の言葉で示そうとしたのは、「生というものはつねに現にあるよりもより強く、より大きくなろうとする、はっきりした方向と内的分節構造をもったもの」(木田元『反哲学史』第十章第三節)という考えです。
2.2 等しきものの永劫回帰
自然に生成という原理を見てとると、世界の様相は永劫に生成し続けながら自分自身に回帰する、という形をとるように思えます。ニーチェは「等しきものの永劫回帰」という言葉でこの事態を示しています。
3.形而上学の克服
ニーチェは人間の認識の本質は、生成している存在者に規則性や形式を当てはめ、それを「図式化」することだ、と考えているようです。ニーチェによれば、認識とは生を確保するために設定された一つの目安にすぎないのですが、伝統的な形而上学はこの設定された価値にすぎない「真理」を超越的存在として実体化して、生をそこに隷従させてきました。そこにニヒリズムが生まれたと考えられます。そうであるならば、いわば捏造された真理へと隷属された自然を、我々の生を可能にしてくれる存在として引き戻す必要があります。
形而上学は精神を肉体から剥離させてしまっているわけなので、肉体を手引きとして新しい存在論を考え出すことが、本来の自然を取り戻す手助けとなってくれるでしょう。ニーチェはこの肉体を手引きとして新たな存在論を成すものを、「芸術」だと考えています。このようにシェリングやマルクスやニーチェのような先駆的な思想家が、西洋形而上学的思考様式を克服しようとしたわけですが、その嫡子といえる技術文明は、むしろ二十世紀に入ってますます猛威を奮うことになります。
4.生成する自然
以上の内容は木田元『反哲学史』第十章第三節を参照にさせてもらっています。一応二冊以上の本は参照にしながらページをまとめているのですが、私に理解できたのはこちらの本のみで、私にこれ以上の哲学的含意の読み取りは難しいです。しかし生成する自然に対するニーチェの思想を、現代の生命理論との関係で考えることならできます。
ニーチェはショーペンハウアーの意志の概念に納得せず、生命のなかにより強くより大きくなろうとする方向性の存在をみてとっています。ニーチェもチャールズ・ダーウィンを参照にしていたらしく、ダーウィンの進化論に対する反論も、ニーチェの力への意志という概念に含まれているようです。
ダーウィンの思想もニーチェのそれと同じくらい誤解されてきたのですが、現在の生物学では概ね原著に沿う形でダーウィンの思想が理解されています。ダーウィンの進化論は、自然の力の流れの中に生命の法則性が生成される様を見出そうとしたものであり、神学を否定するわけではないですが唯物論的な考え方ではあります。ダーウィンは形而上学的な世界の外部にある原理を用いるのではなく、生成され続けることで成り立つものとして生命の流れを記述しようと試みたと思われます。ニーチェは生成する自然の中に、あたかも自明のごとく力の方向性があると見た点において、やはり彼は形而上学者であったと言うべきなのでしょう。
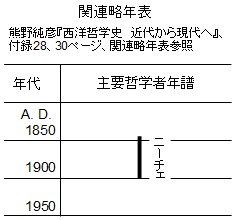
<< マルクスの哲学 近代の哲学まとめ1(知覚・認識論) >>